ノンフィクション作家として世界各地を旅する高野秀行氏。英語から辺境の少数言語まで、今までに25を超える言語を学習。教科書が存在しない辺境の言語はネイティブに学び、文法の法則を自力で見つけ出す「言語オタク」としての経験を基に、新著『語学の天才まで1億光年』(集英社インターナショナル)を22年9月5日に刊行した。高野氏の目に、日本の外国語教育事情はどのように映っているのか。
ノンフィクション作家 高野秀行氏
たかの・ひでゆき。1966年、東京都生まれ。89年に早稲田大学探検部での活動を記した『幻獣ムベンベを追え』(集英社)でデビュー。06年に『ワセダ三畳青春記』(同)で酒飲み書店員大賞を受賞。13年に『謎の独立国家ソマリランド』(本の雑誌社)で講談社ノンフィクション賞、14年に梅棹忠夫・山と探検文学賞受賞。近著に『幻のアフリカ納豆を追え!―そして現れた〈サピエンス納豆〉』(新潮社)など。清水克行との共著に『世界の辺境とハードボイルド室町時代』(集英社)など。
「自分のやり方で解き明かしたい」という原動力
──新著『語学の天才まで1億光年』は高野さんがノンフィクション作家として「辺境」と呼ばれる場所を含む世界各地を旅し、現地で使われる25を超える言語を学んだ特殊な経験を通じて、言語や語学とは何かを考える内容です。そもそもどのような経緯でこのような探検的作風のノンフィクション作家に?
僕が子供だった1970年代は、みんな探検や冒険が好きだったんです。例に漏れず、僕もインディ・ジョーンズや川口浩探検隊、月刊「ムー」(ワン・パブリッシング)など、考古学や探検物語に夢中になりました。人は普通、大人になるにつれてそうした冒険への興味や憧れをなくしていくものですが、なくさないまま大人になる場合もあるということです(笑)
大学で探検部(早稲田大学探検部)に入ると、サハラ砂漠をバイクで横断したり、チベットの遊牧民の村に調査で住み込んだりしている先輩たちがいた。漠然としていた「未知の土地を探索したい」という夢は、そこで一気に具体的になりました。
──高野さんは執筆活動のポリシーに「誰も行かないところへ行き、誰もやらないことをし、誰も書かない本を書く」を掲げています。未知の物事を求め続ける原動力は何でしょう?
今回、本を書きながら人生を振り返って改めて気付いたのは、僕は人から何かを強制されるのが極端に苦手だということです。子供の頃は優等生だったんですが、高校生のときぐらいから、いい大学を出て、いい会社に就職し、そのまま定年を全うするような、決まった生き方が嫌になった。
自分の関心のある物事を、自分のやり方で追い求めて解き明かしたい。「分からないことを分かりたい」という思いが、すべての根幹にあります。それはたぶん、僕の脳内がいつもゴチャゴチャと混乱しているからではないかと思うんです(笑)。だからこそ、分からないことを自分なりに整理したり、解き明かしたり、位置付けたりしたいという思いが人一倍強くなったのではないかと。それが今でも探検的な活動の原動力であり、言語学習も僕にとっては一種の「探検」です。
英語もできなかった青年の言語学習青春記
──過去の著作の中にも、ノンフィクションやエッセイの一部として高野さんが現地の言語を学ぶ過程がしばしば登場していましたが、今回改めて「言語」をテーマに1冊の本を書くに至ったきっかけは?
ある意味、コロナ禍のおかげで書けた本なんです。実はこれまでにも「語学についての本を書いてほしい」とリクエストを頂くことはあったのですが、ずっと海外に行っていたり、取材に基づいて本を書いたりを繰り返す生活で、しっかりと言語学習の経験すべてを振り返ったり、本を書けるほど深く考えたりする余裕はありませんでした。
それが、コロナ禍で海外に行けなくなり、まとまった時間ができた。予期せぬきっかけではありましたが、これまで自分が学んできた語学や、言語とは何かという根本的な問いを、体系立てて考えることができました。僕は20代でアフリカ、南米、東南アジアなどを旅して、それぞれ異なった系統の言語を学びました。言葉にはどういうパターンがあるのか、ある程度までは知っていたことで、説得力を持って語れた点はラッキーでした。
──今までとは趣の異なるテーマを扱う難しさはありましたか?
これまで30作ほど本を書いてきましたが、今作が一番悩みました。「言語や語学に興味がある人」と「過去作と同じような、面白おかしいテイストを求める人」の両方に届けるにはどうすればいいのだろうと。過去作とは方向性を変え、「なぜ日本の語学教育は実践的でないのか?」など、実用的なテーマも検討しました。
ただ、最終的には読者に共感してもらうことを一番に考えました。語学に苦手意識のある人でも、学生時代の英語も話せなかった頃の個人体験から書き始めれば、本を読みながら、僕が言語の魅力にのめり込んでいく過程を一緒に追体験してもらえるんじゃないかと。そう思って記憶をたどりながら書き進めたことで、結果的に青春記としても読める1冊になったと思います。
笑いの生む「距離」がものの見方を豊かにする
──ヒット作となった13年刊行の『謎の独立国家ソマリランド』(本の雑誌社)をはじめ、詳細な調査や経験に基づく内容を、ユーモアを交えて伝える語り口で注目を集めました。なぜジャーナリズムではなく、一貫してエンタメ性の高いスタイルを選んできたのでしょう?
過去には硬派なジャーナリズムを目指したり、藤原新也さんに憧れてシリアスなかっこいい路線を目指したりしたこともありました。でも、どうしても筆が進まなかった。それに、『謎の独立国家ソマリランド』をもしジャーナリズム風に書けたとしても、そもそも日本ではソマリアに興味を持ってくれる人はほとんどいない。それでも多くの人に読んでもらえたのは、やはり「探検記風」だったからだと思うんです。僕が見つけたい答えへとたどり着くまでの過程を、ジャングルをかき分けて進むように追体験してもらうことで、遠い知らない国の話でも共感を持って読んでもらえた。
──作風には「笑い」への一貫したこだわりも感じます。
笑いの本質って「距離」だと思うんです。対象との距離、自分との距離の両方です。例えば、著者が「第3世界のことをもっと理解すべきである」とか「貧しい人たちを助けるべきだ」とか、正論のみで書き進めていくと、客観的な距離のない、公式声明のような「著者=正しい人」という一元的な狭い世界の見方になってしまう。
でも、笑いを取ろうとすると「そんなこと言ってる俺って何なんだよ」という、客観的な突っ込みの視点が入ってきますよね。例えば、学生時代に伝説の怪獣を探しにコンゴを探検した際も、こちらは真剣そのものですが、現地の人からしたら滑稽で笑えるでしょう。だって得体の知れない日本人が、怪獣を探しに来てるわけですから(笑)
現実の世界、あるいは現地での体験は、一本線のような単純なストーリーではなく、反対の意見やノイズや矛盾が複雑に混じり合っている。笑いの「距離」を通すことで、正論だけの痩せた見方ではなく、そうした複数の視点が生きてきて、文章や物語が豊かになっていく感覚があるんです。
この記事は会員限定(無料)です。
【最新号のご案内】日経トレンディ 2022年10月号
【巻頭特集】ずるい! 文章術
【第2特集】Anker大研究!
【第3特集】観光列車ランキング2022
【Special】THE RAMPAGE 川村壱馬 インタビュー
発行・発売日:2022年9月2日
特別定価:700円(紙版、税込み)
■Amazonで購入する
からの記事と詳細 ( 教科書のない辺境言語どう学ぶ 高野秀行氏に聞く語学学習の本質 - 日経クロストレンド )
https://ift.tt/EFevC8K


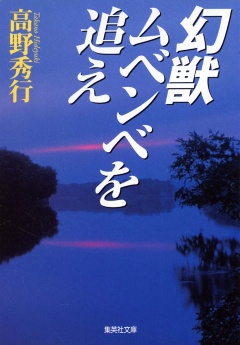
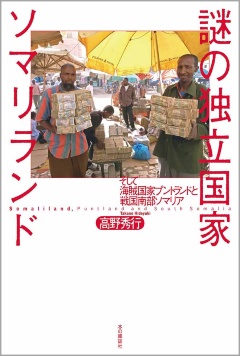
No comments:
Post a Comment